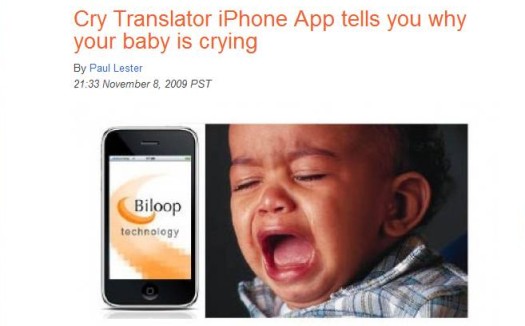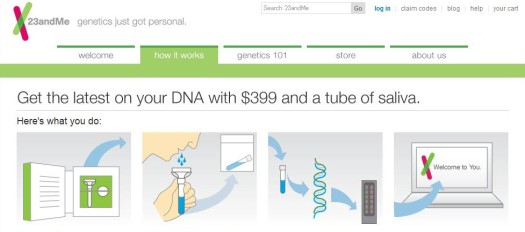GoogleはHHS(米国保健社会福祉省)と協同し、GoogleMapを使って、新型インフルエンザと季節インフルエンザのワクチンを接種できる場所を探すツール「Flu Shot Finder」を公開した。郵便番号か都市名を入力すると、周辺地図に赤と青の注射器マークがマッピングされる。赤は季節インフルエンザ、青は新型インフルエンザ、そして赤青混在は両方のインフルエンザンのワクチン接種拠点を示している。
上図はシカゴ周辺のワクチンマップだが、通常の医療機関だけでなく、MinuteClinicのようなリテールクリニックやWalGreensなど薬局量販店などもワクチン提供拠点になっている。なお、このワクチンマップはまだ全米の20州しかカバーしておらず、また各拠点のワクチン在庫情報表示も遅れがちだということだが、HHSから最新情報の提供を受けて漸次改善していくそうだ。
これは先に公開されたアウトブレークマップと共に、すぐに役立つ便利なサービスだ。これまで医療情報システムと言えば、何か重厚長大でべらぼうにお金のかかるシステムを想像しがちだったが、実際には、こんなふうに状況に機敏に対応する小さくて軽いサービスこそが必要なのだ。
三宅 啓 INITIATIVE INC.