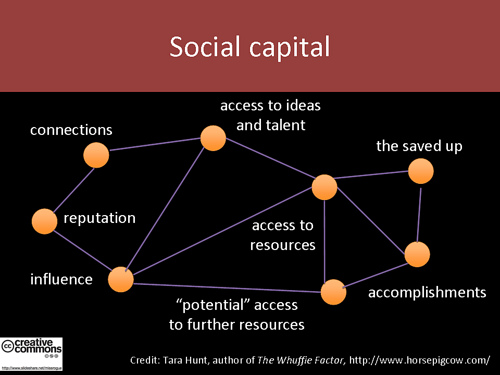今月6日-7日、パリで開催されたHealth2.0ヨーロッパのオープニング・プレゼンテーションが公開された。プレゼンターはマシュー・ホルトとインドゥー・スバイヤが担当したようだ。
導入部の「インターネットの歴史」そしてお決まりの「2.0」のおさらいには食傷気味。本論であるHealth2.0にたどりつくまでが長すぎる。かつて広告業界ではプレゼン冒頭部分(たいていマーケティングスタッフが担当していた)を「祝詞(のりと)」と称していたが、これは短ければ短いほどいいし、できればない方がいいに決まっている。
スライド17で、懐かしいMinitelが出てきたのには驚いた。これは電話帳の代わりにフランス政府が配布したビデオテックスで、1980年代には先進的なニューメディアとして盛んに紹介されていた。当時、日本でも同様のビデオテックス「キャプテンシステム」が登場したが、どちらもいつの間にか姿を消してしまった。 続きを読む