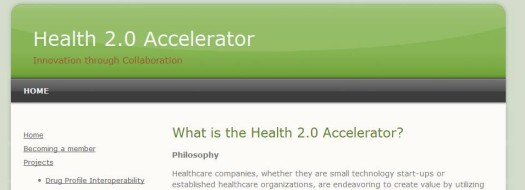ときどき「患者SNSはどうあるべきか?。またそのフィージビリティは?」という議論をすることがあるのだが、米国の状況を見ていると、PatientLikeMeのような特化型患者SNSが成功しているのに対し、いわゆる一般的な汎用患者SNSはさほど成果を挙げていないようである。この点をどう読むかが、患者SNS開発の一番重要なポイントであるだろう。
患者SNSに対するユーザーニーズは、どうやら「似た者同士の交流」というような、誰もがすぐに思いつくものとは、まったく違うものとして考えなければならないのではないだろうか。「心の安らぎ」とか「慰安、癒し」などをシェアする場としてではなく、先日、ニューヨークタイムズがPatientLikeMeの紹介記事にいみじくも付けたヘッドライン「Practicing Patients」が示すように、「アクティブに病気を克服する実践的な活動の場としての患者SNS」という新しいイメージを持つことが、いまや必要になっていると思うのだ。 続きを読む