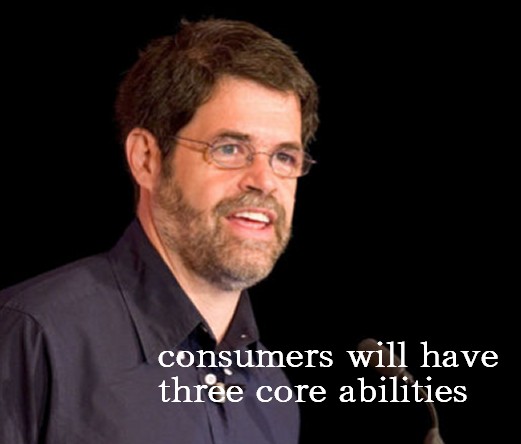一昨日のエントリで、PHRに対する当方の当面の関わり方について述べた。もちろん医療システム全体における中心的役割を、今後PHRが果たしていくことはまちがいない。だが、この春発表された「日本版PHRを活用した健康サービス研究会」(経産省、厚労省、総務省、内閣官房)の総括報告書を読んで、本来のPHRがどのように矮小化されてしまうかを目の当たりにして、失望を禁じ得なかったのである。この研究会とその報告書に対する当方の批判は、こっちのエントリにまとめてある。
その後、「日本におけるPHR」の動向には全く関心がなかったが、一昨日エントリを書いてからGoogleで検索してみると、いくつか関連する出来事が浮かび上がってきた。どうやら「健康情報活用基盤構築のための標準化及び実証事業」というプロジェクトが経産省主導で動き出している模様である。ざっと目を走らせると、「やはり」と言うべきか、「またしても!」と言うべきか・・・とにかくこの種の官庁プロジェクトでは「お決まり」の「公募コンソーシアム」が募集・決定されている。予算は7億円で4つの「コンソーシアム」が決定済み。かつて数年前、厚労省がこの種の「健康関連市場開発コンソーシアム」を多数募集し実施していたが、結局、事業化にたどり着いたものは一つもなかったと記憶している。また個々の「実証実験プロジェクト」の結果がどうであったかも、一向に定かではなかった。果たして公表されたのか?。だが今回、経産省はじめ関係者諸氏は、きっと「結果責任」を取ってくれるのだろう。 続きを読む