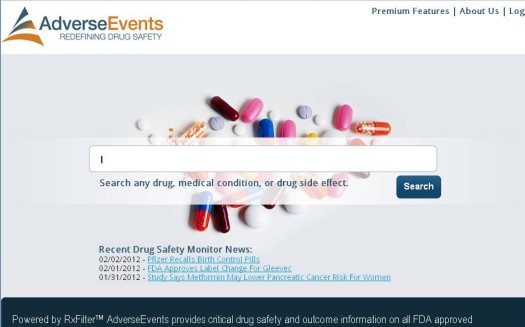厳寒のせいだろう、新宿御苑の梅はまだ硬い蕾で例年よりも開花は遅れている。
前回エントリでEHRの新たな可能性について触れたが、これに関連し、他にもさまざまな方向からのアプローチがあることがその後わかってきた。その中の一つは、EHR上に医療情報サービスの統合プラットフォームを提供しようとするもの。そして今一つは、それぞれのEHRの仕様の違いを越えて患者データをアグリゲートするものである。
上に掲出したCMのDr.Firstは前者のサービスである。もともとこの会社はEHRベンダー各社に対し電子処方箋サービスを提供してきたが、今日ではより広くEHRをプラットフォームとした各種ソリューションの提供をめざしている。たとえば薬剤コンプライアンス・プログラム、患者教育プログラム、薬剤共同購入ディスカウント・サービス、さらには患者の薬歴を集約し医療機関や検査ラボに提供するサービスなどである。 続きを読む