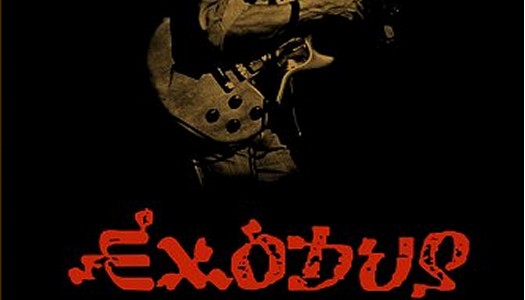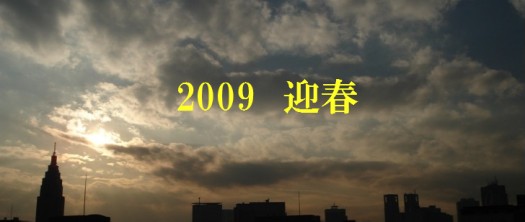いまだ治療方法の確立していない難病は多い。それら難病の患者にとって、インターネットは最も手軽な最新情報ソースとして利用されてきた。昨年11月、英国バーミンガムで開催された第19回ALS/MND国際シンポジウムで、インターネットがALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者や研究者にどのように利用されてきたかを歴史的に概観するプレゼンテーションが患者SNS「PatientsLikeMe」から発表された。
世界各地で1990年代初期のパソコン通信時代から、オンラインでALSの情報交換を行おうとするチャレンジが始められてきたが、インターネットの登場によってその動きは加速され、web1.0、web1.5、web2.0とウェブが進化するのに伴い多彩なサービスが生み出されてきた。短いプレゼンテーションだが、特定の難病をめぐるインターネットの活用方法の進化を、歴史的に概観する貴重な記録となっている。
三宅 啓 INITIATIVE INC.