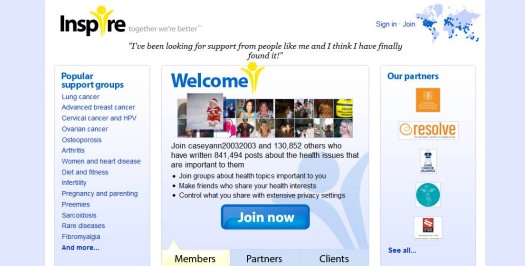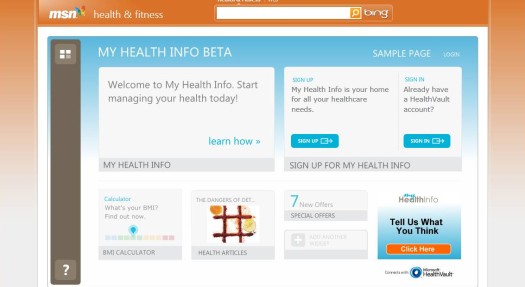様々な試行錯誤が続けられている米国患者SNS市場だが、その中でもInspireはきわめてユニークなスタイルの患者SNSだ。Inspireは、患者支援団体をはじめさまざまな健康・保健団体に疾患SNSスペースを提供している。つまり、Inspireがいわば「大家」としてサイト全体を開発運営し、そこへ「テナント」として健康・保健団体が集まるという構造になっている。ショッピングセンターのデベロッパーとテナントの関係を想起すればよいだろう。
これはある意味で非常に賢いやり方だ。なぜなら、患者会など「テナント」側の会員がそのままInspireの新規会員になってくれることが見込まれ、新たにゼロから会員募集をする必要がないからだ。いわば「テナントが会員を連れてきてくれる」という仕組みになっているのだ。また、それぞれの団体は当該疾患についての専門的な知識・情報・経験を豊富に蓄積しているから、これら資産をそのまま疾患別コミュニティ・サービスに活かすことができる。おまけに有力テナント(著名な健康・保健団体)の知名度や信頼感は、サイト全体の社会的ステータスを上げることに寄与するだろう。また、それぞれのコミュニティの管理運用のほとんどは「テナント」に任せることになるから、デベロッパー側は管理運用負担を大幅に軽減できるわけだ。まさに一石四鳥だ。 続きを読む