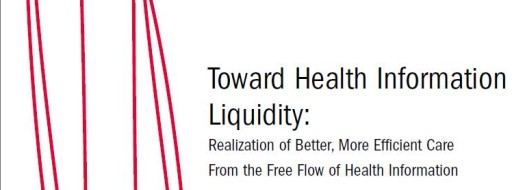昨年末頃から、米国のHealth2.0コミュニティ周辺で「医療情報の流動性」(Health Information Liquidity)という言葉を見かけることがしばしばあった。しかしTOBYOの仕事に没頭していたこともあり、この背景を調べることまで手が回らなかったのだが、なぜか「これは重要な言葉だぞ」という直感があった。
というのは、特に日本で医療情報利用の問題を語るとき、過度に「プライバシー&セキュリティ」というクリシェが持ち出される傾向があり、これに対し少なくない違和感を持っていたからである。むしろ日本では、医療情報のフロー的側面よりも固定的ストックの側面が強調されるあまり、EMRなどクローズドな医療情報システムしか普及しない土壌が出来上がってしまったのではないだろうか。これは「Information wants to be free」というweb2.0以来の新たな情報観に照らしてみて、明らかに逆行する時代遅れのものである。 続きを読む