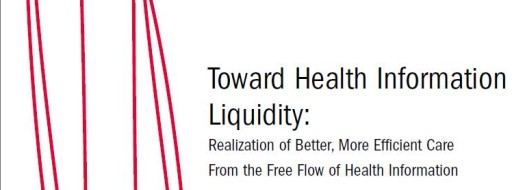以前のエントリで、マイクロソフト社のPHRであるHealth Vaultと新しく開発されたディスプレイ「Surface」のビデオをご紹介した。当方などどちらかと言えば、Health Vaultよりもテーブル型ディスプレイであるSurfaceの方が印象に残ったのだが、新しい紹介ビデオがアップされたのでご紹介しておきたい。 続きを読む
カテゴリーアーカイブ: EHR
mHealthの台頭
最近、海外の医療ブログを読んでいると、しばしば「mHealth」という言葉に出くわす機会が多い。この「m」とは「モバイル」のことで、携帯を活用した医療システムのことを「mHealth」と呼んでいるわけだ。今月、シカゴで開催された医療IT界最大のイベント「HIMSS09」でも、この「mHealth」関連の話題は多く、新商品も多数紹介されていたようだ。
その中でもEHRベンダとして知られるAllscriptsは、同社のEHRをiPhoneでリモートコントロールするソフトを発表し注目されている。ビデオを見ると、ノートPCなどよりもiPhoneの方が圧倒的に操作性は良さそうである。PHRでもこのようなモバイル利用ができれば、消費者の利便性は飛躍的に高まると思える。だが、それではPHRとEHRの棲み分けはどうなるのだろうか。
三宅 啓 INITIATIVE INC.
EHR普及遅れる米国医療界
今週のNew England Journal of Medicineで発表された調査結果によれば、EHR(Electronic Health Records)を導入している米国の病院はわずか9.1%にとどまり、EHRの包括的システムを導入している病院は1.5%、基本システムだけの導入は7.6%であることがわかった。
この調査はハーバード大学公衆衛生学部が実施したもので、AHA(全米病院協会)加盟のすべての急性期医療病院を調査対象としており、回答率63.1%、回答数は3,049病院。また、上記「包括的システム」とは、病院内のすべての診療科に設置されているEHRのことを指し、「基本システム」とは、数か所の診療科だけに設置されているEHRを指している。一般的傾向として、EHR導入実態は病院の「規模、立地、運営形態」と相関があり、導入率が高いのは「大規模病院、大都市立地、大学付属病院」であるとの調査結果になった。
EHRを導入しない病院側の理由は、「資金不足」(74%)、「メンテナンスコスト」(44%)、「医師の抵抗」(36%)となっている。
(以上iHealthBeat March 25, 2009より)
Walmartが医療IT市場へ進出
3月10日付けNewYorkTimes は、Walmartがこの春からEHR市場に本格参入し、価格破壊を医療IT市場に持ち込むと伝えている。これは、オバマ政権が医療IT化刺激策として総額19億ドルのインセンティブを投じることに照準を合わせたものだ。米国医療のIT化は、特に小規模診療所では遅々として進んでいない。その理由として、高い導入コストと操作の複雑化を医師が嫌ってのことだと言われてきた。昨年実施された調査によれば、米国でEMR/EHRなどを医療現場で使用している医師はわずかに17%である。
WalmartはDellとEMR/EHRベンダであるeClinicalWorksと組み、低コストで高機能なシステムの供給をめざしている。価格だが、従来ベンダが提示していた価格のおよそ半額以下になるという。「われわれは”high-volume, low-cost”の企業である。その精神が、医療業界では悲しいまでに欠落している」と、Walmart医療事業開発部門のシニアディレクターであるマーカス・オズボーン氏は述べている。Walmartはこれまでリテールクリニックやコンビニ薬局など医療分野に着々と参入してきたが、とうとう医療機関や医療者を直接顧客とする市場へ進出することになる。 続きを読む
医療情報の流動性
昨年末頃から、米国のHealth2.0コミュニティ周辺で「医療情報の流動性」(Health Information Liquidity)という言葉を見かけることがしばしばあった。しかしTOBYOの仕事に没頭していたこともあり、この背景を調べることまで手が回らなかったのだが、なぜか「これは重要な言葉だぞ」という直感があった。
というのは、特に日本で医療情報利用の問題を語るとき、過度に「プライバシー&セキュリティ」というクリシェが持ち出される傾向があり、これに対し少なくない違和感を持っていたからである。むしろ日本では、医療情報のフロー的側面よりも固定的ストックの側面が強調されるあまり、EMRなどクローズドな医療情報システムしか普及しない土壌が出来上がってしまったのではないだろうか。これは「Information wants to be free」というweb2.0以来の新たな情報観に照らしてみて、明らかに逆行する時代遅れのものである。 続きを読む