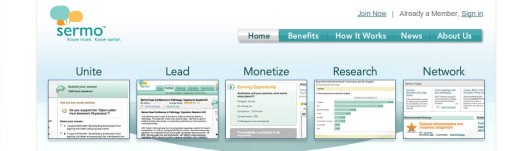先週、ワシントンDCで開催された米国医療法律家協会(AHLA)年次総会において発表されたスライド。発表者はRobert Coffield氏。彼は法律家として「Health Care Law Blog」でHealth2.0の論陣を張ってきている。このスライドではPHRとHealth2.0の位置関係が若干語られているが、少し食い足りない気もする。おそらくPHRは、Health2.0のみならず医療システム全体の基本インフラになるはずなのだが、それを言うのはもう少し先なのかも知れない。 続きを読む
カテゴリーアーカイブ: DATA
「よりパーソナルな医療」へ向かう消費者ニーズ
雑誌「the Journal of General Internal Medicine」6月号に、PHRに関する消費者パーセプションを探る調査結果が発表された。この調査は、ハーバード大学、べス・イスラエル病院、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院、MITなどの専門家によって、全米4ヵ所8グループのフォーカスグループインタビューとして実施された。
調査結果で明らかにされた消費者ニーズを要約すると、次のフレーズになるという。
「私は、この私のことを知っているコンピュータが欲しい」
また、医学的文献をはじめとする医療情報、あるいは今日の医療情報システムが提供している製品やサービスにおいて、最も広範囲に欠落しているのは「普通の人々(regular people)への洞察」であるとしている。さらに興味深い結果として、次の五点が指摘されている。 続きを読む
病院とソーシャルメディア
海外では、ブログ、Twitter、SNSなどソーシャルメディアを活用する医療機関が増えてきている。その動向を知る上で恰好のスライドが公開された。スライド制作者はメリーランド大学メディカルシステムのウェブ戦略ディレクターを務めるエド・ベネット氏。ソーシャルメディアを病院のコミュニケーション活動に活用するためのガイドとして役に立つ。
ところで、日本でこのような活動例をまったく耳にしないのが奇異に思えるのだが、伝統的に日本の病院は社会とのコミュニケーションを等閑視してきたと言えるだろう。海外では、たとえばメイヨークリニックなどは「医療通信社」と言えるほどの規模のコミュニケーション事業を擁しており、マスメディアや社会に向けてニュースやコンテンツ配信を積極的に行っているが、日本ではこのような事例は皆無である。「ソーシャルメディアの活用」云々を言う前に、いまだコミュニケーション活動に対する基本認識の形成段階にあるのが日本の医療の現状と言うべきかもしれない。
三宅 啓 INITIATIVE INC.
米国医師SNSの現状
米国マンハッタンリサーチ社が医師と情報技術に関する調査レポートを発表したが、その中で医師SNSの現状に触れているのが注目される。
同レポートによれば「医師SNSに参加しているか興味を持つ」と答えた医師は60%であり、後の40%は「興味がない」としている。また、既に医師SNSに参加している医師プロフィールの傾向として、同レポートは次のように報告している。
- プライマリケアの医師
- 女性
- PDAか携帯電話を所有
- 診療中あるいは診療の合間にオンライン接続
- 医師平均年齢よりもやや若い層
以上の中で、「女性」が医師SNSの中心メンバーであるとの結果に特に注目が集まっている。これは従来まったく知られていなかっただけに、その原因について、さまざまな仮説が出されているようだ。 続きを読む
Health2.0マーケティングへの接続がベンチャー企業ビジネスモデルに不可欠
11月6日、ニューヨークの医療&製薬市場マーケティング調査会社であるマンハッタンリサーチ社は、調査レポート”Cybercitizen Health v8.0″を発表し、2002年以来米国におけるHealth2.0ユーザーは倍増し、現在6000万人に達していると報告している。このHealth2.0ユーザーだが、マンハッタンリサーチ社では以下のような消費者のことを指している。
・過去12カ月間に以下の行動のうち少なくとも一つを実行した者
- 医療関連のブログや掲示板を読む。医療関連チャットルームに参加する。
- 医療関連ブログを書く、コメントを付ける
- 医療関連フォーラムにトピックを付ける
- 医療関連ウェブページ、ビデオ、音声コンテンツを制作する
- オンライン患者支援団体の掲示板、チャットルーム、ブログを利用する