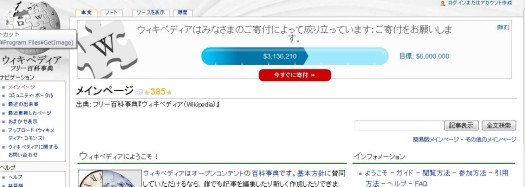目下、闘病記だけを検索対象とする初のバーティカル検索エンジン「TOBYO事典」の開発を進めているが、予定していた12月1日正式公開は12月15日へ延期することになった。その代わりと言ってはなんだが、本日から、これまでテスト運用してきた「TOBYO事典」の全文検索対象サイト数を、暫定的に2061サイトに拡張したのでお試しいただきたい。15日にリリースする正式公開版は、TOBYO収録の1万を越える全サイトを検索対象にする。
約1万件にのぼる闘病サイトのインデクシング作業は先月すでに終了しており、これは全部で約100万ページに達する。ただ検索エンジン自体の最終調整が予想以上に手間取ったために、余儀なく公開延期せざるをえなくなった。 続きを読む