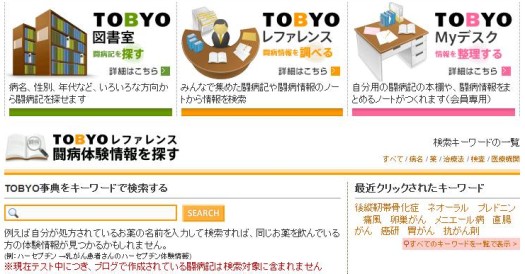たとえば最近出た「リアルのゆくえ」(大塚英志、東浩紀、講談社現代新書)を読むと、「パブリック」をめぐる議論が決して対談者双方の交点を見出すことなく、延々とすれ違いながら展開される光景に呆然としてしまうのだ。「パブリック」という、わかったようで実のところよくわからない概念で何かを語ろうとするとき、どんな議論もどこかですれ違ってしまい苛立ちだけが残る。
それよりも「パブリック、公共性」という言葉自体が、今日こんなに露出してきたのはなぜなのか。前書では次のような発言がある。
「東 ちょっと話を変えますがGoogleというサービスがありますね。ぼくは、むしろああいうものから新しい公共性について考えたいんです。
人間は共同で何か仕事をしないと生きていけないから、人と人を繋ぐテクノロジーは必要である。しかし、そのテクノロジーが、すごく大きく変わるときがある。そもそも国家だって、みんなが国家をつくろうと思ってつくったのではなく、ある技術的条件のなかでなんとなくできあがった共同作業のシステムが、事後的に「国家」と呼ばれ、公共性が見出され、その運営システムが開発されてきたということだと思うんです。そういう観点からすると、いまGoogleのようなウェブサービスは全く新しい共同作業のプラットフォームとしてあって、その運営方法も従来の公共的なコミュニケーションとはぜんぜん違う。しかも、いま現にそれが人々の生活に巨大な影響を与えている。そこには新しい公共性の可能性を感じます。(「リアルのゆくえ」第三章2007年)」