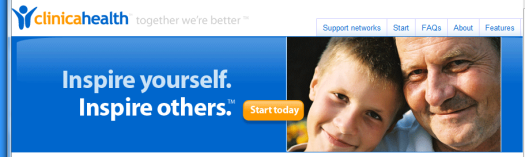
「ClinicaHealth」は患者コミュニティ・サービスの一つだが、その特徴は、患者支援団体(いわゆる「患者会」)にSNSホスティングサービスを提供するというスタイルにある。
いわば患者会ごとにSNSサイトを無料で構築、運用、管理するもので、以下のようなSNS機能が提供される。
・パーソナル・プロファイル
・友人:検索、招待
・ディスカッション
・ブログ
・調査
・メッセージング:メール機能
このようにSNSとしての基本的な機能はカバーしている。「調査」機能だが、これはコミュニティ内部の意見や関心動向の傾向を抽出し共有するものと説明されている。
現在ClinicaHealthは以下のような患者支援団体に対してホスティングサービスを提供している。
・卵巣がんコミュニティ・アライアンス
・クリストファー&ダナ・リーブ財団まひリソースセンター
・肺がんアライアンス
・NORD(難病全国組織)
・ALS協会
・関節炎財団法人
・突然心不全協会
・全国子宮頸がん連合
・ネフローゼ協会
・その他
これら患者支援団体はすでに独自のウェブサイトをすべて持っており、会員に新たなコミュニティ・サービスを提供するためにClinicaHealthを利用しているようだ。いわば自分のところの独自サイトの他に「別館」を持つようなものだ。
日本でも最近、患者会サイト自体を簡易ホスティングするサービスなどが出てきているようだ。このClinicaHealthのような患者会SNSホスティング・サービスも、いずれ出てくるだろう。
ところで「患者会サイト専用のホスティング・サービス」だが、はたして今更提供する意味があるのかきわめて疑問。今日なら、多数提供されている無料ブログホスティング・サービスを使えば、患者会サイトには十分なのでは。「Google Page Creator」のようなものも無料で使える。
一方、患者会SNSだが、その意図はわかるのだが「はたしてワークするのか?」という素朴な疑問がある。患者会のサイズによっては、ユーザーベネフィットを魅力的なレベルで提供しにくいかもしれないからだ。SNSのユーザーベネフィットを基本的に規定するのは、まず単純に「量」であり、これはSNS母集団のサイズのことだ。また、患者会単位でSNSを作ることは、ユーザーグループを細かくセグメントしてしまうことを意味する。
一定のクリティカル・マスをどう想定し、それをどう超えるかが、やはりポイントになりそうだ。その際、「患者会」という単位設定で良いのかどうかが問題となろう。
三宅 啓 INITIATIVE INC.

