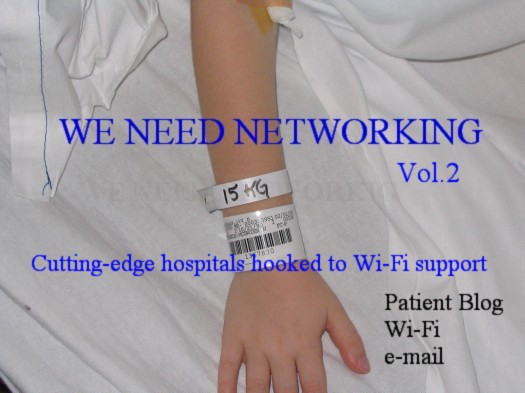
入院患者、外来患者を含む闘病者に対する、ITを利用した医療機関の提供サービスとしては、米国でメイヨークリニックがいち早く「CarePages」という患者向けサービスを始めています。これは特に入院患者およびその家族向けの個人Webサイト開設無料サービスで、
- 家族のためのバーチャル・ミーティング・プレースを作る
- ニュースや写真を共有する
- 必要なときに感情の支援を受け取る
という目的を持って作られています。今後、患者ブログ開設サービスや闘病生活に役立つツールなども提供する予定です。メイヨークリニックは米国でもっともWebサービスに力を入れている医療機関として知られますが、単に情報提供サービスにとどまらず、このCarePagesのような闘病者の主体的活動支援サービスの重要性にも、いち早く気づいているのはさすがです。日本のほとんどの医療機関は、Webで「単に情報を見せる」というような「Web1.0」発想の旧弊から、いまだに抜け出ることができていません。
増加する病院Wi-Fiサービス
先週、シカゴトリビューン紙に、Wi-Fi(無線LAN)サービスを導入する病院が増えていることがレポートされました。
シカゴ大学病院では、2005年2月から子供病院でWi-Fiサービスを無料で提供しており、患者は自分のノートパソコンを持って病院に来るだけで、インターネット接続をはじめさまざまな子供患者向けサービスを受けることができます。シカゴ大学では、傘下の他の病院にもWi-Fiサービスを積極的に導入しており、対象者も入院患者だけでなく外来患者や見舞い客まで拡大しています。
シカゴの医療機関エバンストン・ノースウエスト・ヘルスケアでもWi-Fi導入に力を入れつつあり、今年9月にはエバンストン病院、来年9月にグレンブルック病院、再来年9月にハイランドパーク病院に、Wi-Fiによる患者向けインターネット接続サービスを開始する予定。
またこの医療機関では既にENHfirst.orgという患者向けWebサービスを開始しています。これは無料の患者向けポータルを設置し、会員患者自身の各種検査データの閲覧、担当医とのメール・コンタクト、診察予約、処方箋更新、さらには医療費支払いと費用分析サービスまで提供しており、まさに闘病者にとって実際に役に立つ「使える」サービス内容になっています。
シカゴ地区では、この他にも多数の病院が無料Wi-Fiサービスを開始する予定を持っていますが、これはもちろん患者サービスの高度化という狙いはあるでしょうが、その背景にはWi-Fiの医療機器への影響と誤動作の危険が少なくなったということも指摘されています。日本でもかつて病院での携帯電話使用制限がありましたが、これも徐々に緩和されつつあります。
患者のIT化の盲点
これまで、医療機関のWebサービスは「サイト上にどんなコンテンツを置くか」を中心にデザインされてきたわけですが、逆にユーザー視点から見れば、コンテンツというよりは「使えるサービス」が重要であり、そして大前提として医療現場における「接続」の提供が必要なのだ、という見方が欠落していたと思われます。このあたりが盲点だったのです。
インターネット黎明期から「eヘルス」や「インターネットによる医療サービス」など様々に言われてきた中で、当の病院の現場におけるネット接続の問題が等閑視されていたのは、最大の皮肉といえましょう。これらの言説を今振り返ると、「Webによる遠隔医療」などという発想に顕著なように、何か「地理的に遠隔なものを繋ぐ」というイメージがこれら「eヘルス」論の根っこにあるような気がします。つまり、もともと医療と生活者の間に越えられない「距離」が想定されていて、その「両端をネットで繋ぐ」というアナロジーが立ち上がり、「与える者」と「与えられる者」という関係性が固定されるという文脈において、旧来の医療イデオロギーが反復されていたと考えます。
Webによる新しい医療サービスの可能性は、このような古い医療観を乗り越え、新しい医療と生活者の関係を作りだすところにあるのではないでしょうか。その新しい関係はまだ明確ではないので、私達は、まず闘病者の体験が集約された闘病記に着目しようと考えているわけです。でも、その闘病記も、医療現場の接続環境がなければ書けないのです。やむなく病室のベッドで日々を送っている闘病者に、もし接続環境とノートパソコンが用意されたら、自由に学び表現することができるのです。
三宅 啓 INITIATIVE INC.

