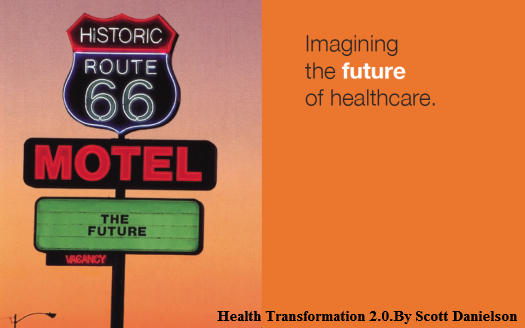大型連休もそろそろ終わりだが、当方はこの連休も、あちこちのウェブ闘病記を渉猟していた。全体として眺めると、なんだか昨年あたりから、新規闘病記ブログが爆発的に増えて来ているような気がする。もし、未来に「医療考古学」というものが存在するとすれば、きっと21世紀初頭の日本は、「歴史上かつてない多数の日本人が、ウェブ上で自分の闘病体験を大量に書き始めた時代」と記されるだろう。これまで自分や家族の病気体験を、このように多数の人が書き出し、公開するような時代はなかったのである。
世界的に見て日本語のブログサイトが突出して多いということは、以前から指摘されてきたのであるが、ウェブ闘病記のこのような増加も、もしかして日本だけの現象なのかも知れない。海外でも「Hospital Diary」とか「Patient Diary」などのジャンルはあるが、どうやら日本のような圧倒的な量的展開には至っていないようだ。一方、米国では患者SNSは多数存在するのだが、日本ではまだほとんど専門の患者SNSサービスは存在しない状態だ。
このあたりの内外比較は非常に興味深い。「なぜ、日本人はウェブで自己の闘病体験を書くのか?公開までするのか?」。このことを、一昨年からわれわれは考え続けてきたが、いまだ確たる結論を見い出せずにいる。今後も考え続けることになるだろうが、とにかく、われわれの眼前に膨大な量の闘病体験が存在している、この事実をしっかりとありのままに直視することが大切だと考えている。
この「膨大な量の闘病体験の存在」という事実から出発して、では、これをどのように活用できるのか、「価値」へと転化できるのか。これらの問いにどう答えるかによって、事業開発の方向は様々に変わってくるのだろう。もちろん多様なアプローチがあって良いのだが、われわれのTOBYOが目指すのは、「膨大な量の闘病体験」を可視化するという、とにかくこのシンプルな一点につきる。
なるほど、日本では「膨大な闘病体験」は「量」として存在する。だがこの「量」は、ただそれだけではまだ社会的な「価値」ではない。まず、全体の可視化が「価値」への第一歩になると、われわれは考えているが、その際、「未来の医療考古学者たちは、われわれが直面している、この時代のこの現状をどのように見るだろうか」と想像してみることがよくある。それはちょうど、上のグラフィックイメージにある「Imagine the future of healthcare」とは、逆向きの視線である。
三宅 啓 INITIATIVE INC.