TOBYO収録闘病サイトは1万2千を超えたが、全体として、闘病ネットワーク圏はどんどん拡大しているという感触がある。今年に入ってから立ち上げられた闘病サイトも多い。最近目につく主な傾向をいくつか拾ってみると、次のようになる。
- メンタルヘルス系闘病サイトの急増
- 複数サイトの使い分け
- 「吐き出しサイト」の増加
まず、闘病サイト全体の中で、メンタルヘルス系闘病サイトが目立って増加している。特に最近は、やはり不況を反映してか、長期病気休暇の末に職を失うケースが働き盛りの30代、40代で顕著であり、事態の深刻さが闘病サイトからうかがえる。また3番目の「吐き出しサイト」にも関連するが、うつ病などの認知療法の一環として闘病サイトを開設する闘病者も多いようだ。「ブログ療法」を医療者が勧めているケースもある。
次に「複数サイトの使い分け」だが、これはたとえばブログ中の闘病カテゴリーを独立させたりして、テーマごとにサイトを使い分けるケースである。身辺雑記と闘病関係を切り分け、記述トーンやサイトイメージなどを整理したいというニーズがあるのだろう。五つ六つのサイトを運営しているケースもざらである。これらは、気分転換にブログサービスを移る「サイト引っ越し」の結果である場合も多い。またこれら複数のブログサイトを管理するために、いわゆる一般ホームページを開設する場合も少なくない。この場合、ホームページが複数サイトのゲートウエイの役割を果たしているわけだ。
そして3であるが、これは昨年の夏ごろから目についてきた傾向である。「吐き出しサイト」とは通常の闘病サイトとは異なり、闘病に関する知識や事実を中心に記録するというよりは、病気に関する不安や不満など感情をストレートに吐き出すことを目的として作られている。これら「吐き出しサイト」を観察してみると、どうやら下記のような共通スタイルがあると考えられる。
- カテゴリーを設定しない
- サイトデザインはカラフルなものを避け無地のものを使う
- エントリ本数が多い: 1000本以上
- 日常の話し言葉で記述される
なぜか以上のような共通スタイルがいつのまにか出来上がってしまったようで、これらは特にアメーバブログで多く見受けられる。「吐き出しブログ」であるから、これらはもっぱら自分自身の不満解消の一助として用いられており、読者(他人)を想定して書かれていなので、カテゴリー設定がなかったり、デザインやレイアウトの配慮がなかったり、ぶっきらぼうな語り口で書かれていたり、総じて読者の便宜を図ろうという気遣いがないのである。したがって「闘病の知識と体験の共有」という面では、きわめて扱いにくいコンテンツであるというほかない。ユーザーの感情の吐露が中心になっているのだから、記録的な価値は低いと言えるかもしれない。
ある意味で他者とのコミュニケーションを放棄したような「吐き出しサイト」の登場は、明らかに従来の闘病ネットワーク圏のカルチャーとは異質なものである。これをどのように評価すべきか、しばらく見守りたい。
三宅 啓 INITIATIVE INC.

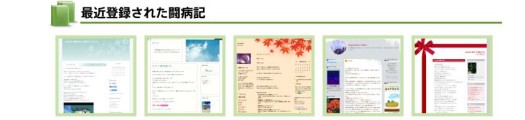

ご指摘の傾向、大変興味深いです。
質問です。ご指摘の「吐き出しブログ」の書き手には例えばTwitterのユーザに見られるような、「ゆるいつながり」を求めているという傾向はないのでしょうか?
相対的に濃いつながりと言えるmixiのようなコミュニケーションは気ぜわしいが、他者とつながっていたいという意思は捨てていないのではないかと推察しました。
インターネット上にメッセージを放つという手段をとる以上、どこかで読み手を期待しているという図式から私は離れられないです。ノートに日記を書くときに図らずも読み手を意識してしまうように。